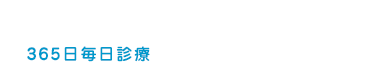4種混合・ヒブワクチンのネット予約休止について
母子手帳をご用意のうえ、お電話でご相談ください
適切なワクチンを提案、予約します
電話番号:03-6231-8388
【受付時間】
平日・土曜:9:30〜12:00、13:45〜17:15
日曜・祝日:10:00〜12:30、15:00〜16:15
現在、4種混合ワクチンの流通が終了し、当院への卸業者からの供給が停止されたため、急遽ネット予約を中止しました
あわせて、ヒブワクチンのネット予約も休止中です。
2024年1月以前にお生まれの方へ(4種混合ワクチン未完了の方)
4種混合ワクチンの接種が4回に満たない方は、今後の接種スケジュールに調整が必要です。
● 対象となる方
- ✔︎ 2024年1月以前に出生
- ✔︎ 4種混合ワクチンの接種が未完了(4回未満)
● ご予約方法
4種混合ワクチンを単独で接種される場合
お電話にてご相談ください。
ヒブワクチンの接種歴との関係もあるため、母子手帳をご準備のうえご連絡ください。
※母子手帳をお持ちいただければ、直接来院してご相談いただくことも可能です。
4種混合ワクチンとヒブワクチンを同時にご希望の場合は、「5種混合ワクチン」での接種となるため、WEBから予約が可能です。
「5種混合ワクチンを接種してよいかわからない場合」は、事前に母子手帳をご用意のうえ、お電話でご相談ください。
当日お越しいただいてから5種混合ワクチンの接種ができないと判明した場合、当日の接種ができないことがありますので、あらかじめご了承ください。
今後の対応について
お子さんのこれまでの接種状況に応じて、以下のように対応いたします。
◆ 4種混合・ヒブともに接種回数が残っている方
5種混合ワクチンで対応可能な方は、原則こちらを使用します。
◆ ヒブワクチンをすでに4回接種済みで、4種混合が残っている方
5種混合は使用できないため、以下の方法で対応します。
5種混合が使用できず、4種混合ワクチン在庫終了時の対応
ヒブワクチンをすでに4回接種済みの場合、5種混合は使用できず、また4種混合も在庫がない場合は、以下のワクチンを組み合わせて対応いたします:
- 3種混合ワクチン(ジフテリア・百日せき・破傷風)
- ポリオワクチン(単独)
ただし、
・3種混合ワクチンも在庫が非常に少なく
・ポリオワクチンは常備しておりません
ため、すぐの接種が難しい可能性があります。該当の方は取り寄せまでにしばらくお待ちいただく可能性があります
5種混合ワクチンは在庫があります(対象:2024年2月以降の出生児)
2024年2月1日以降にお生まれの方は、5種混合ワクチン(4種混合+ヒブの一体型)を使用しているため、今回のお知らせの影響はありません。
これまで通り、5種混合ワクチンでご予約ください
ご案内
本件は、4種混合ワクチンの製造終了による全国的な事情であり、今後の供給再開見込みはありません。
対象となる方は、お子さんの母子手帳をご確認のうえ、お電話または直接ご来院のうえご相談ください。