予防接種
 予防接種を受けるのは何故?
予防接種を受けるのは何故?
予防接種(ワクチン)は、病気にならないように免疫をつくるものです。 予防接種を接種することで、かからなくて良い病気や合併症からお子さんを前もって守る唯一の方法です。
病気になって後悔しないためにも、接種できる年齢になったら速やかに接種しましょう。
予防接種には、本人がその病気にかからないようにする事と、かかっても軽く済む目的があります。
さらに、周りの人にうつさないためにという社会的目的も併せ持ちます。
 当院で接種可能な予防接種
当院で接種可能な予防接種
定期接種(公費負担)
- ・ ヒブ(Hib)
- ・ 4種混合(DPT-IPV)
- ・5種混合ワクチン(4種混合+ヒブ)2024.4.1〜
- ・ロタウイルス
- ・ 肺炎球菌
- ・ B型肝炎ワクチン
- ・ BCG
- ・ MR(麻疹、風疹)
- ・ 水痘(みずぼうそう)
- ・ 日本脳炎
- ・子宮頸がん
- ・二種混合(DT)
任意接種(自費負担)
2024年4月更新
※問診票がダウンロード出来ない場合は、受付にご用意しておりますので、お声がけください
※生後2ヶ月の初めてのワクチンでは、ヒブ、肺炎球菌、4種混合ワクチン、B型肝炎ワクチン、ロタリックスを接種してください。当院では同時接種を推奨しています。
【髄膜炎菌】【三種混合】【狂犬病】【A型肝炎】各ワクチンはこちらをお読みください
 ご予約
ご予約
予防接種は予約なしでも可能(日本脳炎・インフルエンザワクチン除く)ですが、ご予約の方が優先となります。
当院に受診したことがない方(診察券がない方)でもインターネット予約可能です。
●スマホをお持ちの方は、 アプリで「アイチケット」を入手すると、より予約は簡単になります
アプリ入手は、「アイチケット」のページから←クリックして移行
接種スケジュールなど、ご不明な点があれば母子手帳を持参の上、お気軽にご相談ください
※【ロタテック】【単独ポリオ】、その他 予約画面の選択肢にないワクチンをご希望の方は
お電話(03-623I-8388)でご予約ください
当日お持ち頂くもの
・母子手帳
・予防接種票(区から郵送される問診票)
・保険証
・医療証
※ 定期予防接種の場合、母子手帳をお忘れの際は接種できません
※ 定期接種の場合、予防接種票に記載されている有効期限内であれば無料で接種可能です
※ 15歳以下の方の接種には、予診票に保護者の署名が必要になります。 16歳以上の方については、親の同意書は必要ありません。 中学生以下の接種においては、原則、保護者の同伴が必要となります
※15歳以下の高校生で単独にて予防接種を希望される場合は予診票に保護者の署名と予防接種同意書が必要になります
同意書はこちらからWEB上で記入してください
※ 保護者以外の方(祖父母、お友達の方、保育士、ベビーシッターなど)が付き添いで予防接種を希望される場合はワクチン1種類につき1枚の委任状が必要となります。江戸川区に提出するため紙の委任状に保護者が手書きで記入してください
 予防接種を接種する際の注意事項
予防接種を接種する際の注意事項
- 接種可能かどうかは当日の診察にて判断します。熱が37.5度以上ある場合は、接種出来ません。熱性疾患のあとや痙攣(けいれん)後などは、痙攣後一定期間をあけて接種が望ましいです。事前にご相談ください。
- 重篤な副反応がおこりやすいのは接種後30分くらいです。
急な変化に対応できるよう一定時間は院内にて滞在していただきます。
その後も30分は、すぐにクリニックと連絡が取れるようにしておいてください。 - ワクチン接種前には、配られる冊子「予防接種と子どもの健康」などを読んでいただき、受診してください。
読んでわからないことなどあれば、医師・看護師にお気軽にご相談ください。 - 保護者以外の方(祖父母、お友達の方、保育士、ベビーシッターなど)が付き添いで接種に来られる際、予防接種では委任状が必要になります。
委任状は、予防接種の当日までに、保護者本人及び同伴する方が署名し、接種日当日に同伴する方が予防接種票とともに医療機関に持参してください。
委任状は接種後、予防接種票とともに江戸川保健所の担当まで提出されます。
委任状の有効期限は、委任状に記載された日から1か月以内となります。医師の診察・説明を受けた後、接種に同意する場合は、予診票の保護者自署欄(同意欄)に、同伴者本人の署名をすることになります。 - お子さん1人での受診について 原則として、未成年の方の予防接種は保護者の同伴が必要です。高校生以上で単独受診での接種を希望される場合は接種希望欄への保護者自筆の署名がされている問診票に加え、接種同意書が必要になります。
接種希望欄への保護者自筆の署名した問診票と接種同意書両方持参された場合のみ接種をおこないます。 - 接種時期が接種推奨年齢から外れている場合は、接種回数や有料無料が異なる場合がありますが、できるだけ接種することが望ましいです。接種スケジュール、公費負担可能かどうかのアドバイスの相談をおこないますので、お手持ちの問診票、母子手帳を持参の上受付までお越し下さい。
 よくある質問
よくある質問
Q.予防接種のメリットとデメリットは何ですか?
メリット
現在、日本で接種する予防接種はいずれも規定回数接種することでかなりの確率で免疫ができ、病気にかかりにくくなります
感染した場合でも、自然にかかるより、軽症ですむ可能性が高いです
デメリット
接種時に痛みをともないます
接種による副反応があります
多くみられるのは、発熱や接種部位の腫れ、かゆみなどです。
極めて可能性は低いものの接種後早い段階で、血圧が下がる、呼吸が苦しくなるといったアナフィラキシーを起こす可能性があります。
Q.予防接種を同時に多数接種しても大丈夫ですか?
多数の予防接種を同時に接種しても、ひとつひとつ別々に接種しても副反応の可能性は倍増するわけではありません。副反応の可能性は同じですし、効果も減弱することはありません。全ての予防接種をどの組み合わせで、何種類同時に接種しても組み合わせや本数で問題になることはありません
Q.予防接種したあと熱が出ました。次回の接種は控えた方がよいでしょうか?
発熱や接種部位の腫脹のようなよくある副反応であれば、予防接種のメリットのほうが大きいため、次回も接種したほうがよいと思われます。ただし、副反応の程度によりますので、詳しくは医師に相談してください。
Q.副反応は何がありますか?
比較的可能性の高い副反応、可能性は低いが起こりうる副反応、予防接種の影響かどうか不明ではあるが、報告されている副反応の3つにわけられます。比較的可能性の高い副反応として、不活化ワクチン(ヒブ、肺炎球菌、4種混合、B型肝炎、インフルエンザワクチン)では接種部位の腫れと、熱があり、当日でることが多いです。腫れは3日程度、熱は1日で自然におさまります。生ワクチン(MR、水痘、おたふくかぜワクチンなど)では腫れや熱がすぐでることはなく、むしろ1週間程度して熱や発疹がでることがあります。こちらも熱は1日程度、発疹は3日程度で自然によくなります。
Q.予防接種のスケジュールを教えてください。
下記におおまかな接種スケジュールを記載します。予防接種後は一定期間をあける必要がありますので、接種日に次の予定をたてるようにしましょう
まずは生後2ヶ月になったら速やかにヒブ・肺炎球菌・4種混合(DPT-IPV)・B型肝炎・ロタウイルスワクチンを接種しましょう
そして1歳の誕生日を迎えたら速やかにMR(麻しん・風しん)・水痘・(おたふくかぜ:任意)ワクチンを接種しましょう
生後2ヶ月 : ヒブ①、肺炎球菌①、4種混合①、B型肝炎①、ロタリックス①
生後3ヶ月(1回目から4週間後) : ヒブ②、肺炎球菌②、4種混合②、B型肝炎②、ロタリックス②
生後4ヶ月(2回目から4週間後) : ヒブ③、肺炎球菌③、4種混合③
生後5ヶ月 : BCG
生後7ヶ月 : B型肝炎③
1歳 : MR①、水痘①、(おたふくかぜ①任意)
1歳4ヶ月頃 : ヒブ追加、肺炎球菌追加、水痘②、4種混合追加(1歳4ヶ月になる月の初旬におくられてきます)
3歳 : 日本脳炎①②
4歳 : 日本脳炎追加
5〜6歳(年長さん) : MR②、(おたふくかぜ②任意)
9歳 : 日本脳炎2期
11歳 : DT(2種混合)
12〜13歳(女子) : 子宮頚がんワクチン①②
Q.インフルエンザワクチンはいつ接種するのがよいですか?
インフルエンザワクチンは13歳未満のお子さんは2回接種が必要です。1回目と2回目の間隔を2週間あければ接種可能ですが、免疫をできやすくするために4週間程度あけるのが望ましいです。2回目接種後2~4週間して、免疫ができ効果は接種後4~5ヶ月は高く維持されることを考えると、毎年流行が始まる12月~2月の1ヶ月前には接種完了しておくことがのぞましいです。
そうした理由から2回接種が必要(13歳未満)な方は、1回目を10月中下旬、2回めを11月中下旬にされるのがよいと考えます。13歳以上の方は、11月初旬に接種がのぞましいと考えます。ただし、接種が遅くなっても、効果がないわけではありませんので、大流行の状況でなければ年内は1回目の接種をおすすめします。
Q.風邪薬などを飲んでいたら接種できないですか?
ステロイドや免疫抑制剤服用している場合は接種出来ないこともありますが、多くの薬剤は服用中でも接種可能です。かかりつけ医に接種可能か相談してください。
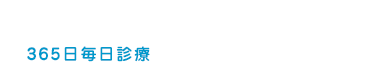
 予防接種
予防接種