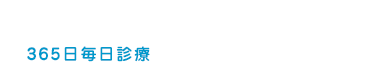RSウイルス感染症とは|いつよくなる?家庭でできるケアと乳児の注意点を解説
RSウイルス感染症はどれくらいで治る?家庭での過ごし方や受診の目安を解説します
RSウイルス感染症は、特に乳児で注意が必要な呼吸器の感染症です。発症から3〜5日目に咳や呼吸症状が悪化し、生後6か月未満の赤ちゃんでは哺乳困難や呼吸困難をきっかけに入院が必要となることもあります
一方で、多くのお子さんは家庭でのケアで回復が可能です。症状のピークがいつなのか、どれくらいで改善するのか、兄弟がかかったときの家庭内の注意点など、このページでは保護者の「今知りたいこと」に答える形で、RSウイルス感染症について解説します。
RSウイルスとは?
RSウイルス(Respiratory Syncytial Virus)は呼吸器のウイルスで、特に乳幼児で重症化しやすい感染症です。
多くの子どもが2歳までに一度は感染するといわれており、珍しいウイルスではありません。
主な症状と経過
最初は鼻水や微熱、咳といった風邪のような症状から始まります。
数日以内に咳が強くなり、ゼーゼーとした呼吸(喘鳴)、痰のからみ、哺乳困難が目立つようになります。
年齢による特徴的な症状:
・生後6か月未満:発熱はあまり目立たず、ゼーゼー、呼吸困難(哺乳困難や呼吸の荒さ)が主な症状です。
呼吸の苦しさは発症から5〜6日目で一番悪くなりその後ゆっくり回復します。
・1歳前後:発熱が続き、ゼーゼーが徐々に悪化する経過をとることが多くなります。
発熱がはっきりと現れ、38℃〜39℃台の高熱になることもあります。発熱は通常2〜4日でおさまることが多いですが、個人差があり、4〜6日ほど続くこともあります
ゼーゼーのピークは0歳と同じく5〜6日目です。
治療について
RSウイルスに対しての特効薬はなく、治療はすべて対症療法です。
- ▪️ 去痰薬や気管支拡張薬で呼吸を楽にする内服薬を処方することがあります
- ▪️ 生後5か月以上で高熱がつらい場合には解熱剤(アセトアミノフェンなど)を使用します
- ▪️ 自宅での繰り返しの鼻吸引や室内の加湿も効果的です
- ▪️ 呼吸困難が強い場合や哺乳ができない場合は、入院して酸素吸入や点滴を行います(入院しても根本的な治療はありません)
家庭内での予防(兄弟が発症したとき)
RSウイルスは家庭内感染が多く、特に兄姉から乳児への感染が目立ちます。以下の予防策を取りましょう。
- ▶︎ 乳児と感染した兄弟はなるべく別室で過ごす、寝具も別にする
- ▶︎ 赤ちゃんに触れる前には、家族全員が石けんで30秒以上の手洗いを徹底する
登園・登校の目安
RSウイルス感染症は学校保健安全法の出席停止疾患には含まれていませんが、以下の状態を目安に登園を再開しましょう:
- ✔︎ 解熱後24時間以上経過している
- ✔︎ 哺乳や食事が普段の7割以上に戻っている
- ✔︎ 夜間の咳き込みが強く、睡眠が十分とれない場合は、もう少し自宅で様子を見ることをおすすめします
RSウイルス感染症の診断(迅速検査)について
RSウイルス感染症は、治療法がないためすべてのお子さんに行うものではありません。
当院では以下の場合を参考に医師の判断で検査を実施しています:
- ▪️ 生後3か月未満の赤ちゃんなど、重症化リスクが高いと判断された場合
- ▪️ 診断によって入院などの治療方針を決める必要がある場合
- ▪️ 基礎疾患があり重症化リスクの高い場合
RSウイルス迅速検査を全員に行わない理由
- RSウイルスは、発症の1~2日前から感染力があり、症状が改善したあとも1~3週間ウイルスを排出します
- したがって、診断をつけたからといって感染対策の区切りが明確になるわけではなく、RSウイルスの診断を行って全員を隔離すること自体に意味がないというのが国際的な標準です
早めに受診すべき症状
以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください:
早めに受診すべき症状
以下のような症状がある場合は、すぐに医療機関を受診してください:
- ▶︎ 哺乳量が急に減った(目安として通常の半分以下)
- ▶︎ 呼吸がはあはあと速い、胸がへこみながら呼吸している(陥没呼吸)
- ▶︎ 哺乳すると顔色・唇が紫色になる
- ▶︎ ぐったりしている/反応が鈍い
新しい予防の選択肢
妊娠中の母親対象ワクチン:アブリスボ
妊娠28〜36週の妊婦に接種することで、胎児に抗体が移行し、生後のRSウイルス感染を防ぎます。
現在のところ当院ではアブリスボの接種は行っていません。
RSウイルス感染と乳児喘息の関連性
乳児期のRSV感染は、その後の喘息発症リスクを高める可能性があることが、複数の研究で示されています。特に、生後1年以内の感染は喘息の発症リスクが増大します。
当院についてのご案内
M’s(エムズ)こどもクリニック瑞江は、東京都江戸川区にある年中無休の小児科です。
赤ちゃんから高校生まで、咳、気管支炎、ゼーゼー、長引く熱に関する診察も対応しています。
診察時間やアクセスの詳細は、当院ホームページをご確認ください。