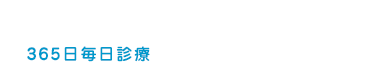日本脳炎は“今もある病気”です 〜重い病気を防ぐために、今できること〜
日本脳炎って、昔の病気だと思っていませんか?
そう感じている方も多いかもしれませんが、実は今でも国内で発症することがある“重い感染症”です。発症例は少ないものの、一度かかると命にかかわる、あるいは後遺症が残る可能性のある病気であるため、予防接種がとても重要です。
● 日本脳炎とは?
日本脳炎は、蚊(主にコガタアカイエカ)によってうつるウイルス感染症です。感染しても多くの人は無症状ですが、100〜1,000人に1人の割合で脳炎を発症します。
- 発症した場合、死亡率は約20〜40%
- 回復しても約半数に後遺症(けいれん・運動障害・知能障害など)が残ります
まれにしか起こらないけれど、非常に重い病気です。
● 日本ではもう流行していないの?
たしかに日本では、以下のように大きな流行は減少しています:
- 1966年:2,017人(ピーク)
- 1992年以降:毎年10人以下
しかし、1999年以降には10代・30代・40代と比較的若い世代でも患者が発生しており、油断はできません。
● 今もウイルスは国内に存在しています
厚生労働省では、毎年夏に豚の抗体調査を行っています。日本脳炎ウイルスは豚の体内で増殖し、それを吸った蚊が人に感染させます。
その調査により、毎夏ウイルスを持った蚊が国内に発生していることが確認されており、感染の機会は今も残っていると考えられています。
● 特異的な治療法がなく、予防が最重要
日本脳炎には特異的な治療法がなく、対症療法が中心です。症状が出た時点でウイルスはすでに脳に達しており、脳細胞の破壊が始まっています。
仮に将来ウイルスに効く薬が開発されても、一度壊れた脳細胞は元に戻らない可能性が高いのです。
予後についても、30年前と比べて死亡率は減ったものの、「完全に回復する例」は全体の約3分の1と、ほとんど改善していないのが現状です。
だからこそ、日本脳炎は“予防こそが最大の対策”です。
● ワクチンを受けていなかった人が多い
近年の患者のデータから、日本脳炎を発症した人の多くが、ワクチン未接種であったことがわかっています。裏を返せば、ワクチンによって防げた可能性が高いのです。
● 接種スケジュール(標準的な例)
- 第1期初回:3歳で2回(6日以上あけて)
- 第1期追加:4歳で1回
- 第2期:9歳〜10歳(小学4年頃)で1回
※蚊の発生が早い地域では、生後6か月から接種を開始することもあります。
● まとめ:日本脳炎は“かからないこと”が何より大切
日本脳炎は、発症する確率は低いものの、一度かかると重症化しやすく、治療も難しいという特徴があります。
発症してからの治療ではなく、かかる前にしっかり予防することが、お子さんの命と健康を守るために最も大切です。
予防接種は公費で受けられる定期接種のひとつです。対象年齢のうちに、忘れずに接種を済ませましょう。
よくある質問
Q1. なぜ1回目の接種は3歳からなのですか?
日本脳炎ワクチンは生後6か月から接種可能ですが、標準的な開始年齢は「3歳」とされています。その背景には以下のような理由があります:
- ⚫︎ 過去の発症年齢分布からの知見: 長年の疫学調査により、日本脳炎の発症は主に3歳以上の小児に多く見られ、3歳未満での発症は非常にまれであったため、リスクの高い年齢から接種を始める方が合理的とされました。
- ⚫︎ 免疫応答の安定性: 3歳以降の方が免疫系が成熟しており、ワクチンによる免疫獲得がより安定して期待できると考えられています。
- ⚫︎ 他の定期接種との兼ね合い: 乳児期にはヒブ、小児肺炎球菌、4種混合、BCGなど多くのワクチン接種が集中しています。それらが一段落する3歳頃が、次のステップとして合理的なタイミングとされました。
Q2. 生後6か月から接種が勧められるのはどんな人ですか?
標準的には3歳からの接種ですが、以下のような場合は生後6か月からの接種が推奨されることがあります:
- ▶︎ 日本脳炎ウイルスの常在地域(特に西日本)に住んでいる
- ▶︎ 夏季に日本脳炎の流行地域へ長期間滞在する予定がある
- ▶︎ 近隣に養豚場があり、豚との生活空間が近い(豚はウイルスの増幅動物です)
- ▶︎ 地域の保健所や医師から接種を勧められた場合
これらに該当する場合は、かかりつけの医師と相談のうえ、接種時期を判断することが大切です。
Q3. 接種スケジュールが遅れてしまいました。どうすればいいですか?
接種が遅れてしまっても、年齢が定期接種の対象年齢内(第1期は7歳6か月未満、第2期は13歳未満)であれば、公費で接種が可能です。
ワクチンは途中で間が空いてしまってもそれまでの接種は有効であり、最初からやり直す必要はありません。未完了の分を追加接種することで、十分な免疫をつけることができます。
特に第1期(3回)の接種がまだ終わっていない場合は、気づいた時点でできるだけ早く接種することが重要です。夏季は蚊の活動が活発になり、感染のリスクが高まるためです。
母子手帳を持参のうえ、医療機関で接種履歴を確認し、残りの回数を速やかに接種しましょう。
Q4. 第1期追加(3回目)を7歳で受けた場合、第2期はいつ受ければよいですか?
第1期(初回2回+追加1回)まで接種が完了していれば、基礎免疫は確実に獲得されていると考えられます。基礎免疫の持続期間は約5年間とされており、標準スケジュール(追加接種が4歳)であれば、5年後の9〜10歳で第2期を接種するのが合理的です。
しかし、第1期追加が7歳と遅れた場合、その直後に第2期(9歳)を接種すると、まだ免疫が高いままであり、2期としての効果が低い可能性があります。
第2期は1期追加から3〜5年ほど間隔をあけて接種する方が、追加免疫としての効果が高いと考えられます。
ただし、定期接種の対象年齢である「13歳未満」までに第2期を完了することが必要です。これを過ぎると任意接種(自費)扱いになります。
接種時期の調整については、医師と相談しながら、最も効果的かつ確実なタイミングで受けるようにしましょう。
土日も予防接種を受け付けています
エムズこどもクリニック瑞江(江戸川区)では、平日午前午後に加えて土日も予防接種を受け付けています。
予約方法や受付時間は、当院ホームページからご確認いただけます。