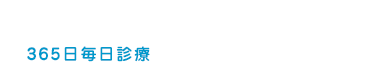子どもの喘息治療|発作を減らす薬の使い方と長期管理のポイント
小児喘息の治療について
〜発作を減らし、安心して過ごすために〜
喘息の治療は、発作をできるだけ少なくし、お子さんが毎日の生活を快適に過ごせるようにすることが目的です。そのためには、「発作が起きたときに使う薬(発作治療薬)」と、「ふだんから使って発作を予防する薬(コントロール薬)」を正しく使い分けることがとても大切です。
■ 治療の基本方針
気管支喘息の治療の基本は、次の3つに集約されます:
- 発作時には、気道をすばやく広げる薬と炎症を抑える薬を使って、症状をしっかり抑えること
- 日常的には、発作を起こさないように予防する薬(長期管理薬)を継続すること
- 良くなったように見えても、自己判断で薬をやめず、医師と相談して治療を調整していくこと
このように、気管支喘息では状態に応じて薬を使い分け、炎症を抑え込む治療を継続することが大切です。
■ 発作時に使う薬(リリーバー)
喘息の発作が起きたときには、呼吸を楽にするための薬をすぐに使うことが大切です。
【1】メプチンシロップ(プロカテロール)
短時間作用型β刺激薬(SABA)です。服用してから30分〜1時間ほどで効果が現れ、約8〜12時間持続します。朝と夕の2回の内服で、日中や夜間の発作に対応できるため、ご家庭でも使いやすい薬です。
【2】吸入薬(ベネトリンやメプチン)
すでに吸入器をお持ちの方や、必要な場合にはクリニック内で使用します。即効性があり、症状を速やかに和らげます。
【3】デカドロン(デキサメタゾン)
発作が強いときには、ステロイドの飲み薬を短期間(通常3〜5日間)だけ追加して使用します。飲んでから30分〜1時間ほどで効果が現れはじめ、12〜24時間ほど効果が続きます。1日1〜2回の服用でもしっかり効くため、特に夜間の発作や長引く咳がある場合に有効です。
■ 発作を予防する薬(コントローラー)
- 吸入ステロイド薬(ICS)
- アドエア(ICS+LABA配合剤):朝夕2回の吸入で炎症と気道収縮を予防します。
- パルミコート(ブデソニド):家庭で吸入器(例:オムロンNE-C28など)を使用して吸入します。
- ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA):キプレス、シングレア、モンテルカスト、プランルカストなど。ロイコトリエン拮抗薬は飲み薬で、特に幼児期に使いやすいため、多く使用されています。ただし、喘息発作そのものをすぐに止める薬ではなく、発作の予防や長期的なコントロールを目的とした薬です。
通常、1〜2週間で効果が現れ始めますが、毎日継続して飲むことが大切です。効果を安定させるために、当院では症状が落ち着いていても、はじめてから最低3か月間は継続して服用するようにご案内しています。
効果が出てきたからといって自己判断でやめず、医師の指示に従って続けるようにしましょう。
- ツロブテロールテープ(ホクナリンテープ):この薬は 長時間作用型の気管支拡張薬 で、咳止めとは異なります。喘息のお子さんでは、夜間の咳や症状が安定するまでの間に 補助的に使用 され、症状の経過に応じて中止や継続を判断します。
■ コントロール時の実際の治療方法
幼児(小学生未満)では吸入操作が難しいため、まずは飲み薬から開始し、症状に応じて治療を段階的に強化していきます。
【1】ロイコトリエン受容体拮抗薬(LTRA)
飲み薬として使用。症状が軽度であればこの薬のみで安定することもあります。
【2】吸入補助具(スペーサー)を使ったアドエア吸入
補助具を使った吸入で、導入しやすく一定の効果があります。ただし薬剤が全量吸入できない場合もあり、効果が不十分となることがあります。
【3】吸入器を使ったパルミコート吸入
吸入器(例:オムロンNE-C28など)を使用し、確実に薬剤を気道に届ける方法です。より高い効果が期待できます。
吸入器のメリット:確実な吸入が可能で、夜間の発作にも自宅で対応できます。
吸入器のデメリット:購入が必要で、将来的に使わなくなる可能性があります。また、1回の吸入に約5分かかるため、忙しい朝の使用が負担になることもあります。
小学生以上では吸入が可能であれば、アドエアディスカスを基本として導入します。まだ難しい場合には、幼少児と同様の治療(LTRAや吸入器など)を行います。
■ 治療の見直しについて
当院では、漫然と薬を続けることがないように、症状が安定している場合には定期的に治療の見直しを行っています。
おおよそ3か月間発作がなく安定していれば、保護者の方と相談のうえ、治療を段階的に減らす(ステップダウン)または中止することを検討します。
中止したあとに再燃して薬を再開することもありますが、それでも心配はいりません。
発作のない状態を何度も経験することで、いずれは薬を使わずに過ごせるようになるお子さんがほとんどです。
焦らず、お子さんのペースに合わせて、医師と一緒に治療を進めていきましょう。
当院についてのご案内
M’s(エムズ)こどもクリニック瑞江は、東京都江戸川区にある年中無休の小児科です。
赤ちゃんから高校生までの喘息、長引く咳、ゼーゼーに関する診察も対応しています。
診察時間やアクセスの詳細は、当院ホームページをご確認ください。