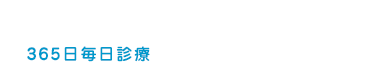アナフィラキシーとは?子どもの重いアレルギー反応とその対応・日常生活の注意点を解説
急なアレルギー症状に備えて|アナフィラキシーの正しい知識と家庭でできる対策
アナフィラキシーとは、食べ物や薬、虫刺されなどが原因で起こる、急激で全身に広がる重いアレルギー反応です。じんましんや呼吸困難、吐き気、ぐったりするなど複数の症状が短時間であらわれ、命に関わることもあります。特に子どもでは食物が原因になることが多く、初めての症状でも重くなることがあるため、早めの対応と正しい知識が重要です。
アナフィラキシーの診断
アナフィラキシーは、アレルゲン(食べ物・薬・虫さされなど)に触れたあと、短時間で全身に急激な症状が出るのが特徴です。診断は、血液検査よりも症状の出方や時間経過が重要とされており、以下のような症状が2つ以上みられた場合、アナフィラキシーが疑われます。
- ▶︎ 皮膚や粘膜の症状(じんましん、赤み、かゆみ、口の腫れなど)
- ▶︎ 呼吸器の症状(せき、息苦しさ、ゼーゼー、声のかすれなど)
- ▶︎ 消化器の症状(腹痛、吐き気、下痢など)
- ▶︎ 循環の症状(顔色が悪い、意識がもうろうとする、ぐったりなど)
血液検査(IgE抗体検査)は、アナフィラキシーの診断には使われません。診察時には「何をきっかけに、どのような症状が、どれくらいの時間で出たか」を詳しく伝えることが重要です。
アナフィラキシーの薬剤
アナフィラキシーの経験があるお子さんには、再発に備えて医師からあらかじめお薬が処方されることがあります。これらの薬は、いざというときにすぐ使えるように、日頃から必ず携帯してください。
- ▪️ 抗アレルギー薬(抗ヒスタミン薬・ステロイドなど)
かゆみやじんましん、軽度の症状を抑えるために使われるお薬です。症状が出たときにすぐ内服できるよう、常に持ち歩くようにしてください。 - ▪️ エピペン(アドレナリン自己注射薬)
アナフィラキシーの症状が急激に進んだときに、命を守るために使う注射薬です。症状が重いと感じたら、迷わず使用し、その後すぐに救急車を呼んで医療機関を受診してください。エピペンは医師の診察を受け、必要と判断された場合に処方されます。なお、エピペンは体重15kg以上の方が対象であり、小さなお子さんには医師と相談の上で判断されます。
アナフィラキシーを起こしたときの対応
- ! エピペンを持っている場合は、ためらわずにすぐ使用します。
- ! すぐに119番で救急車を呼びます。「アナフィラキシーの可能性があります」と伝えてください。
- ! 安静にし、足を少し高くして仰向けに寝かせます。
- ※たとえ症状が落ち着いても、必ず医療機関で診察を受けてください
- ※エピペンを使用した場合は、必ずそのことを医師に伝えてください。使った本体も持参しましょう。
- ▶︎ エピペンや抗アレルギー薬は、発作時にすぐ対応できるよう必ず携帯し、使い方を日頃から確認しておきましょう。宿泊学習や外出時は特に注意が必要です。
- ▶︎ アレルギーについては、本人だけでなく、家族や学校、保育園など周囲の人にも伝えておくことが大切です。給食やおやつの場面での誤食を防ぎ、お友だち同士のお菓子の交換などによるトラブルも避けることができます。
- ▶︎ 学校や保育園・幼稚園には、事前にアレルギーの内容と対応方法を共有しておきましょう。「学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)」を医師に作成してもらい、提出することで、集団生活でも適切な対応が受けられます。
- ▶︎ 外食や旅行など慣れない環境では、必ず原材料やアレルギー表示を確認し、スタッフに口頭でも伝えるようにしましょう。事前に安全なメニューを調べておくと安心です。
- ▶︎ 食事から除去する食品がある場合でも、栄養バランスが偏らないように代替食品を上手に取り入れましょう。ご家族で同じものを一緒に食べる工夫をすることで、お子さんが孤立感を抱かず、楽しい食事につながります。
- 1位:鶏卵(33.4%)
- 2位:牛乳(18.6%)
- 3位:小麦(8.8%)
- 4位:くるみ(7.6%)
- 5位:落花生(6.1%)
- 6位:イクラ(4.9%)
- 7位:カシューナッツ(2.9%)
- 8位:えび(2.5%)
日常生活での注意点とやるべきこと
アレルギーの原因となる食品について
現在、日本で表示が義務付けられている「特定原材料(8品目)」は以下の通りです:卵、乳、小麦、そば、落花生(ピーナッツ)、えび、かに、くるみ(2025年4月より完全義務化)。
特にくるみは、近年アレルギーの報告数が増加し、アナフィラキシーなど重症例もあることから、2025年4月より表示が義務化されました。
消費者庁による全国調査(令和3年度)では、アレルギーを引き起こした食材の上位は以下のようになっています。
アレルギーの症状や重症度は個人差があるため、原材料表示の確認に加え、気になる食品がある場合は医師に相談の上で除去や対策を行うことが大切です。
一度食品を除去すると、再び食べ始めるのが難しくなることがあり、不必要な除去は栄養面や生活の質において本人に大きな不利益をもたらす可能性があります。
特に乳幼児の場合は、自己判断せず、必ず医師の診断のもとで除去や管理を行ってください。
食物アレルギーの診断と除去についてはこちらのページをご参照ください:
▶︎ 食物アレルギーは血液検査だけではわかりません|正しい診断と除去の判断基準