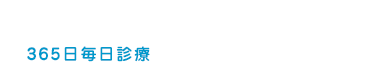食物アレルギーは血液検査だけではわかりません|正しい診断と除去の判断基準
食物アレルギーと血液検査について
血液検査で「食べられるか・食べられないか」がわかると思われている方が多くいらっしゃいますが、これは正確ではありません[1]。
血液検査で陽性という結果が出た場合、それは「その食品に対して感作されている(反応を起こす準備がある)」ことを示しますが、実際に症状が出るかどうかとは一致しません[1][2]。
つまり、陽性でも食べられることはよくありますし、逆に陰性でも症状が出ることもあります[1][3]。
食物アレルギーの診断には、まず詳しい問診(症状の内容や、食べてからの時間、年齢、体調、食べ方など)が重要です。
そのうえで必要に応じて血液検査を行い、診断の参考にします。
特に注意すべきなのは、「血液検査が陽性だった」「何となく心配だから」などの理由だけで食品を除去することです[3]。
病歴がなく、症状もない場合に自己判断で除去することは、成長に必要な栄養を制限してしまう可能性があります。
これまで問題なく食べられている食品であれば、検査は必要ありません。そのまま食べ続けていただくのが望ましいです。
保育園などに通い始める前に
保育園などで給食が始まる場合、これまでご家庭で食べたことのない食品は、園で初めて食べることができません。
園で出る食材については、事前にご家庭で午前中(なるべく平日)に、加工された単品を極少量だけ食べさせてみてください。
食物アレルギーがある場合は、多くが食後30分~2時間以内に症状が出現します。
・顔全体や目のまわりの腫れ
・全身のじんましん(虫刺されのような発疹)
・強いかゆみ、掻きむしり、不機嫌
・嘔吐、咳、ゼーゼー(喘鳴)
口のまわりだけが赤くなる場合は、食物アレルギーではなく接触による皮膚炎の可能性もあります。
自己判断せず、医師にご相談ください。
症状が出たときは、皮膚の状態をスマートフォンなどで撮影しておくと、医師が診断しやすくなります。
当院についてのご案内
M’s(エムズ)こどもクリニック瑞江は、東京都江戸川区にある年中無休の小児科です。
赤ちゃんからこどもの食物アレルギーの相談も対応しています。
診察時間やアクセスの詳細は、当院ホームページをご確認ください。
食物アレルギーの指示書は当院かかりつけのお子さんのみ記載しています
参考文献・出典
- [1]日本小児アレルギー学会. 食物アレルギー診療ガイドライン2021
-
[2]American Academy of Allergy, Asthma & Immunology (AAAAI).
https://www.aaaai.org -
[3]厚生労働省. 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)
厚生労働省公式サイト(アレルギー対応ガイドライン)
出典・参考文献の要約
1. 日本小児アレルギー学会「食物アレルギー診療ガイドライン2021」
- 血液検査(特異的IgE抗体)は「感作(sensitization)されているか」を示すのみであり、臨床症状の有無とは一致しないと明記されています。
- 診断のためには、食物経口負荷試験が最も信頼性の高い方法とされています。
「特異的IgE抗体価が陽性であっても、症状がなければ食物アレルギーとは診断しない。
実際に症状があるかどうかは、問診や負荷試験で確認する必要がある」
2. 米国アレルギー・喘息・免疫学会(AAAAI)
- IgE抗体検査について、偽陽性が多く、単独でアレルギー診断には使用できないことを強調しています。
“Positive specific IgE test alone does not confirm a food allergy diagnosis.”
(特異的IgEが陽性でも、それだけでは診断は確定しない)
3. 厚生労働省. 保育所におけるアレルギー対応ガイドライン(2019年改訂版)
- 血液検査で数値(IgE抗体値)が高くても、必ずしも症状が出るとは限らないことが明示されています